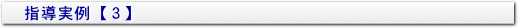 |
| �� |
�ؒ둁�c�����@�̏ꍇ�@�i�ی�ҁ^��Ј��j |
| �E |
���k���^
�ؒ낳��������́A���R���鍂�Z�R�N���������B
|

����搶�Ɩؒ낳��
(����16�N6��12���B�e)
|
| �E |
�w���̃|�C���g�^
�Z���^�[������Ƃ��āA����搶�ɉp����A��X�搶�ɐ��w���A���ꂼ��T�P�A�v�T�Q��̃y�[�X�ŁA���P�̒�N�ƈꏏ�Ɏ�u�B�w���͑��c����𒆐S�ɍs��ꂽ�B
|
| �E |
���c����̊��z�^
�w�ǂ���̐搶�����J�ɂ킩��₷���A�v�搫�������ċ����Ă���܂��B��X�搶���w�̎��Ԃɂ́A�Ƃ��ǂ��A���w�̂킩��Ȃ��Ƃ���������Ă�����Ă��܂��B�e�ʂ̂�����̏Љ�ŒÎR�i�w�[�~�i�[���ɗ���ł����A�ǂ���̐搶���ƂĂ��^���ŁA�v�����Ƃ���̐搶�ł��B�w�����e�ɂ͑�ϖ������Ă��܂��B�x
|
| �E |
���̌��^
�����̎�����w�ɍ��i�B���݁A�[��������w�������߂����Ă���
|
|
���w���ꏊ������ɂ�
���w����������P�O����
�����w���������P�Q�O����
���w���Ȗ����p��A���w�A���w�A�p�ꃊ�X�j���O etc... |
|
|
|